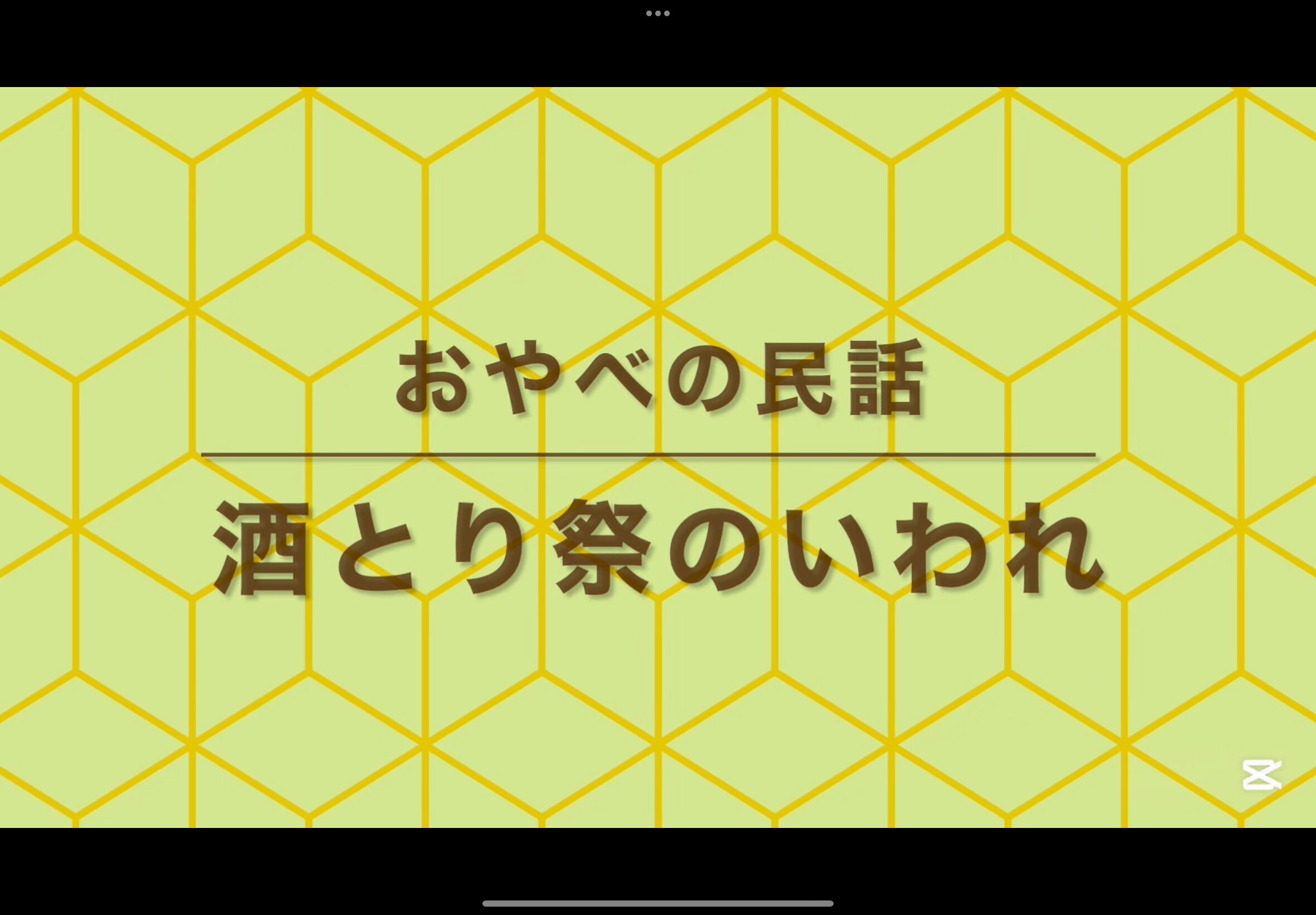毎年4月の第4日曜日に行われる下後亟神明宮の春祭り「酒とり祭」は全国でも珍しい風習が残る奇祭として知られている。
25歳の厄年の青年たちが、真新しい褌に白鉢姿も勇ましく参道から歓声をあげて神殿へと走り込み、檜づくりの柄杓で酒を汲み、参道の参詣人老若男女の誰彼かまわず飲ませて回る。境内いっぱいに歓声や奇声が広がる。青年たちは争って神殿の酒を汲んで振舞いまわるが、果は境内一面にばらまく。青年たちは、酒を汲む回数が多い者ほど、参詣人や見物人は酒を多くかけられたほど、その年は幸が多いといわれ、勇壮な中にも神秘的なお祭りである。
この奇祭の起源は不明であるが、今から350年ほど前の寛永年間(1625~44)に現在の社殿を建立したとき、地中より白骨が多く発掘された。これは墓所であったに違いないと人々は不安を感じた。特に村の物知りな老人が酒を撒いて祈祷しなければ一大事が起こると言った。しかし村人たちは気に止めながらも、つい忘れてしまった。ところが翌年、村はじまって以来と言われる大凶作に襲われてしまった。あの時の老人の言葉を思い出し、きっと白骨のたたりに違いないとばかり、村総出で酒を撒き清めたという。これがこの奇祭の起源だとも伝える。
ところが明治2年(1869)になり、「酒をぶっかけたりばらまいたりするのはもったいないことだ。そんなことをするより、みんなで飲んだ方がどんなに得かわからない。」ということで、村人たちは境内にむしろを敷き、車座になって飲めや歌えやのどんちゃん騒ぎをやってしまった。
これが神の怒りに触れたのか、その年は不作も不作、その上、村に火災が頻繁に起こった。すっかり恐れをなした村人たちは翌年から、今まで以上に盛大な酒とり祭を執り行ったということである。
住所 : 〒932-0101 富山県小矢部市下後亟640
駐車場なし(住民の方々のご迷惑にならない様注意しながら周辺に停車してください)